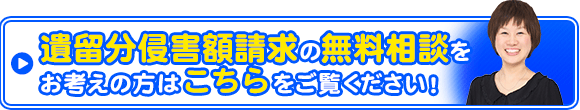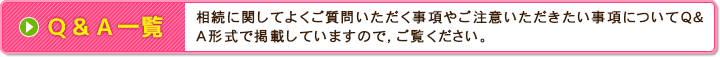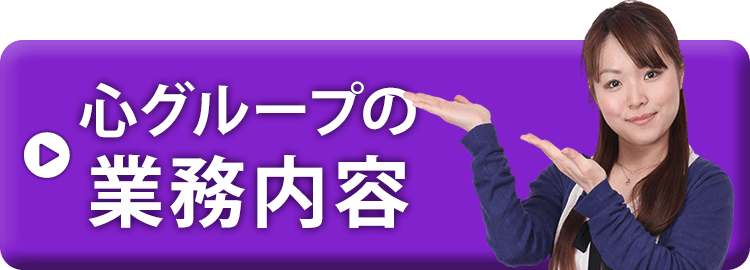遺留分の放棄
1 遺留分を放棄してもらいたい場合
現在の日本の法律では、遺言書を作成したとしても、必ずそのとおりに遺産を配分できるとは限りません。
一部の例外を除き、相続人には、遺留分という権利が保障されているため、遺産をあまりもらえなかった相続人は、遺産を多くもらった相続人に一定の権利(遺留分)を請求できます。
しかし、相続人同士で揉め事が起きることを防ぐため、遺言書を書いた人がご存命のうちに、相続人の方に遺留分の権利の放棄をしてもらうことが可能です。
なお、遺留分の放棄は、遺留分を放棄する相続人の協力があって初めて、手続きが行えますので、協力が得られない場合は、この制度を使うことはできません。
協力が得られない場合は、相続人の廃除や遺留分対策を検討することになります。
2 生前の遺留分の放棄の手続き
遺留分は、法律で認められている権利を、あらかじめはく奪する制度であるため、家族間で話し合いをするだけでは、遺留分の放棄はできません。
遺留分の放棄をするためには、遺留分を放棄する相続人自身が家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可
そのため、遺言書を作成した方が相続人に代わって遺留分の放棄を行うこともできません。
手続きをする家庭裁判所は、遺言書を作成した方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、遺言書を作成した方が名古屋にお住まいの場合、名古屋家庭裁判所で手続きを行います。
また、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる場合、遺言書を作成した方の財産内容等を書面に記載する必要があります。
3 生前の遺留分の放棄が認められる条件
⑴ 自分の意思に基づくこと
遺留分の放棄をする人が、自らの意思で手続きを行う必要があります。
例えば、家族に圧力をかけられたり、強要されたりしたような場合は、遺留分の放棄はできません。
⑵ 遺留分の放棄に合理的な理由や必要性があること
遺留分の放棄は、特定の相続人に対し、最低限保障された権利をはく奪する制度であるため、放棄をさせる以上は、それ相応の理由が求められます。
例えば、長女はすでに十分な生前贈与を受けており、残った遺産を次女に相続させるためというような事情が挙げられます。
⑶ 遺留分の放棄をするにふさわしい対価を受け取っていること
遺留分に相当する程度の財産を、放棄する人に渡しておく必要があります。
例えば、「次女は会社の役員で、自分で十分な資産を築いているから、遺産を渡す必要はない」と考え、遺留分の放棄を申し立てても、認められない可能性があります。