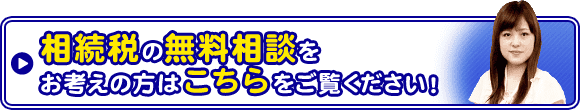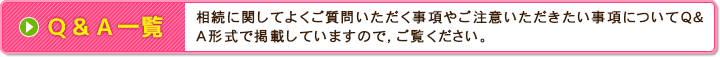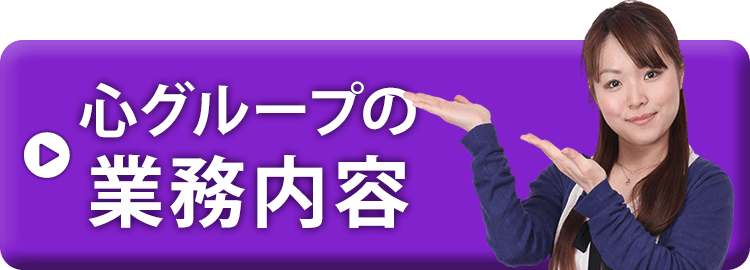弔慰金が相続税の対象になる場合
1 弔慰金は原則として相続税の対象とならない
人が亡くなった際に、その遺族らに対して、葬儀の場で香典や花輪・供花代、葬祭料などとして金銭が支払われることがあります。
葬儀の場では、死者に対する弔いの気持ちであったり、葬儀を主宰し、葬儀代を負担する喪主への贈与であったり、様々な趣旨で金銭が支払われており、その名称は、名古屋やその他の地域によって異なるほか、葬儀の方式によっても様々なものがあります。
葬儀の場だけでなく、その後、勤務先等から弔慰金の名目で金銭が支払われることもあります。
このような弔慰金が相続税の対象となることは原則としてありません。
2 例外的に相続税の対象となる場合がある
勤務先から支払われる弔慰金は、場合によっては非常に高額であることがあり、名古屋の会社でもこのような例はしばしばみられるところです。
弔慰金が相続税の対象となることは原則としてありませんが、以下のような場合には、例外的に相続税の対象となります。
まず、被相続人の雇用主などから弔慰金の名目で金銭を受け取っていたとしても、その実質が退職手当金などに該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
また、認められない場合においても、その金銭の額が、一定額を上限として、上限を超える部分が退職手当金等として相続税の対象となります。
一定額とは、被相続人の死亡が業務上の死亡であるときには、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額となり、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときには、死亡当時の普通給与の半年分に相当する額とされています。
ここでいう普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
参考リンク:国税庁・弔慰金を受け取ったときの取扱い
3 退職手当金等として扱われた弔慰金の処理
上記のとおり、弔慰金は退職手当金等と扱われる可能性があります。
退職手当金等とは、被相続人の死亡によって受け取った、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与のことをいい、名古屋の会社でもこのような規定のある会社は多くあります。
退職手当金を受け取っていた場合には、退職手当金の額と退職手当金等として扱われる弔慰金の額の合計が、みなし相続財産として相続税の対象になります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金
相続税を適切に申告・納付しなかった場合のペナルティについて 相続で弁護士をお探しの方へ