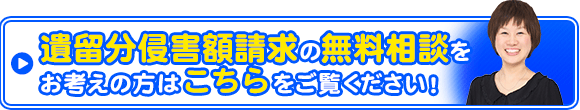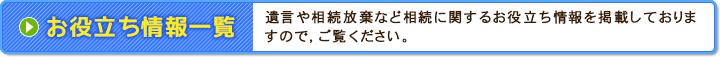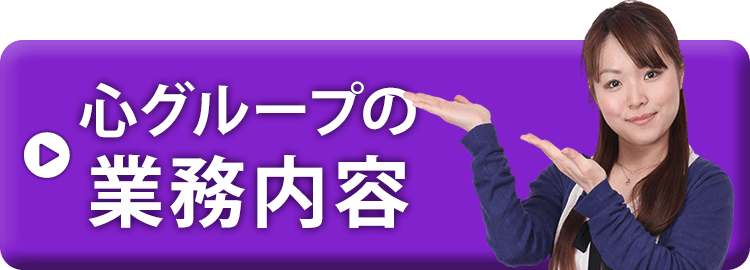遺留分を請求された場合についてのQ&A
遺留分を請求する内容証明郵便が届いたのですが、金額が記載されていません。どうすればいいですか?
遺留分侵害額請求には、消滅時効という期間制限があります。
この期間は、自らの遺留分が侵害されていることを知ったときから1年とされています。
遺留分を請求する側にとっては、この期間内に遺留分の請求をする必要があるのですが、請求をするときまでに請求額がはっきりしないことがあります。
消滅時効が生じないようにするための請求においては金額を明示しなくてもよいとされているため、金額を明示しない遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届くことがあります。
このときには、相手に請求額をはっきりしてもらったうえで、相手との金額の交渉をすることになります。
不動産しか相続していないのに、遺留分として金銭を支払うように請求されています。金銭の代わりに不動産を渡すことはできないのですか?
現在の制度では、遺留分の請求は、遺留分侵害額請求権という権利になっており、金銭の支払いを請求できる権利になっています。
そのため、遺留分の請求を受ける側は金銭で支払う必要があります。
ただし、相手方との交渉で、金銭の代わりに不動産を譲渡するということが合意できれば、そのような内容で解決することもできます。
私以外にも相続をした相続人はいるのですが、私だけが遺留分を支払わないといけないのでしょうか?
遺贈や贈与などの内容が遺留分を侵害するものであった場合に、それぞれの内容を計算して、その遺留分侵害額が分かったとします。
遺贈や贈与が複数であった場合には、どの内容の遺贈や贈与を受けたかによって遺留分侵害額請求の対象になるかが変わってきます。
たとえば、相続人に対する複数の遺贈が対象になる場合には、遺留分侵害額は、それぞれの相続人の遺留分を超えた部分に応じて按分されることになります。
この計算方法はかなり複雑ですので、このような問題がある場合には、専門家に相談されるのがよいでしょう。
遺留分の時効に関するQ&A 遠い親戚から相続放棄してほしいと連絡があったのですが、どうすればいいのですか?