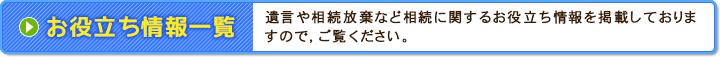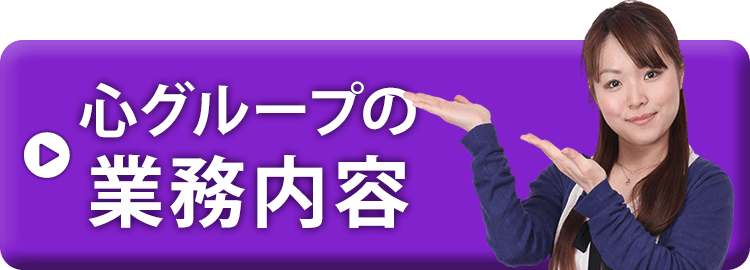相続人調査に関するQ&A
なぜ相続人調査が必要となるのですか?
亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で協議した上で、亡くなった方の不動産の名義を変更したり、預貯金を解約したりする必要があります。
これらの手続きを進めるためには、遺産分割協議書という書類が必要になります。
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産をどのように相続するかを記載した書面をいい、相続人全員で作成する必要があります。
したがって、仮に、相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
初めから相続人全員で協議を行い有効な遺産分割協議書を作成するため、相続手続きを進めるためには、相続人を正確に調査する必要があるのです。
どのような人が相続人になるのですか?
亡くなった方の相続人に誰が該当するのかは、法律で定められています。
まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
また、第1順位の相続人は亡くなった方の子どもです。
そのため、例えば、亡くなった方に妻と2人の子どもがいた場合には、その3人が相続人になります。
亡くなった方に、その方よりも先に亡くなった子どもがおり、その子どもに子どもがいた場合には、その孫にあたる者が相続人になります。
この場合、亡くなった子どもの配偶者は相続人とはなりませんので注意が必要です。
なお、子どもには、実子だけでなく養子も含まれます。
第2順位の相続人は直系尊属です。
直系尊属とは、亡くなった方の親などにあたる方をいいます。
つまり、亡くなった方に子どもがおらず、親が存命であれば、その親が相続人になります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
亡くなった方に子どもも親もいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
このように、配偶者を除いて相続人となる優先順位が決まっており、高い順位の相続人がいなければそれより後の順位の人が相続人となります。
相続人はどのように調査すればよいですか?
相続人を調査するためには、戸籍を取り寄せる必要があります。
亡くなった方の相続人を調査するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
戸籍は市町村役場で取得することができます。
亡くなった方の本籍地がどうしても分からない場合には、市町村役場で住民票を取得することで本籍地を確認できます。
法律の改正、転籍、婚姻などによって戸籍は新しく作成されるため、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍は、一通では済まず、基本的に複数あることとなります。
相続人が、第2順位、第3順位となった場合には、その分必要な戸籍も増えます。
また、遺産分割協議を行わないまま長期間が経過した場合には、取り寄せる戸籍の数は膨大になることがあります。
なぜなら、亡くなった方の子どもがその親の遺産分割協議をしないまま亡くなっている場合、この子どもの相続も発生することとなり、親の相続のときと同様、この子どもが生まれた時から亡くなるまでのすべての戸籍が必要となるためです。
したがって、時間が経てば経つほど、このような事態となっている可能性は高まります。
相続人調査のために戸籍を取り寄せる際には、何十枚もの戸籍を読み解き、役所に問合せをするケースもあり、手間と時間がかかることも珍しくありません。
相続人調査はどのように依頼すればよいですか?
相続人の調査は、相続手続きの第一歩です。
相続人調査のためには、時には明治時代や大正時代までさかのぼって、膨大な数の戸籍を用意する必要がありますし、昔の難解な戸籍を読み解く知識・経験や時間が要求されることもあります。
そのような場合には、相続人ご自身で相続人調査を進めることは困難になるかと思いますので、ご負担を減らすためにも、弁護士などの専門家にご相談をいただければと思います。
相続開始後の預貯金口座の凍結に関するQ&A 登記ができない遺言書に関するQ&A